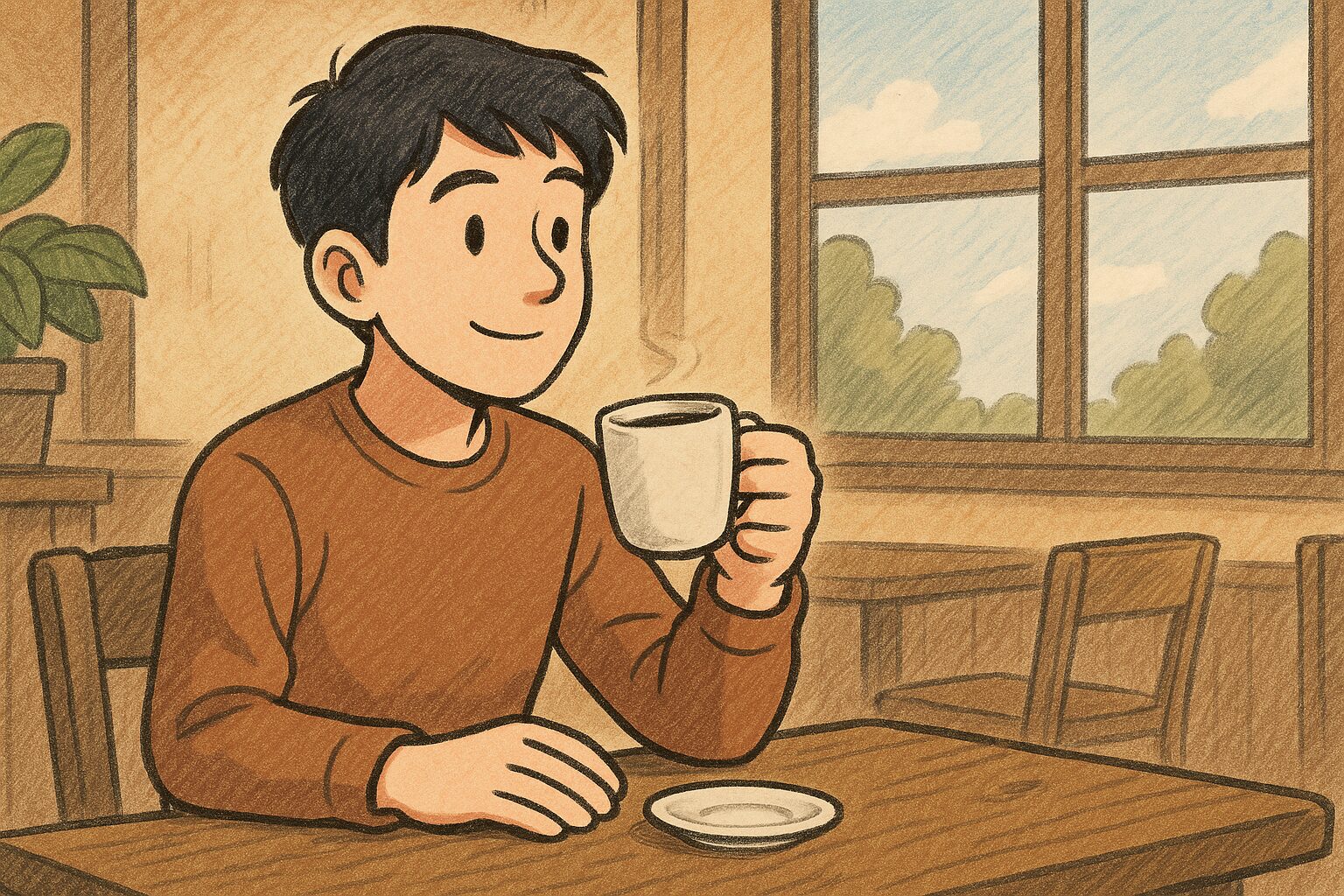ちょっとした疑問から始まったChatGPTとのやりとりが、いつの間にか思考の整理と行動のヒントになっていた──。この記事では、PDCAの捉え方をテーマに、思考の深まりや集中環境の工夫について、自分の体験と対話を通してたどった記録をまとめてみた。
ChatGPTと対話でひもとく「PDCAの本質」
きっかけは、ふとした疑問から
「何か行動をしたとき、結果が出るときと、出ないときがある。
その違いって、いったい何なんだろう?」
ある日、そんなことを考えていた。
たとえば移動した距離や使った時間──これは明確に“行動した証”として見える。
だけど、得られる結果には差がある。
移動先で誰かと会ったとか、何かを得たという“成果”があるときもあれば、ただ疲れただけのときもある。
「行動と結果の関係って、いつも正比例するわけじゃないよな」
そう考え始めたら、いろんなことが気になってきた。
「数値化できる結果と、できない結果ってあるよね?」
「知識って数値化できないけど、テストにすれば点数として扱える」
そんなことをメモ帳に書きながら、ふと思った。
「これ、PDCAで言うと、どこまでが“P(計画)”なんだろう?」
ChatGPTとの対話スタート
ChatGPTに聞いてみた。
返ってきた答えは、こうだった。
今考えていることは、PDCAの“P(Plan)”の前半から中盤くらい。
目的や評価の軸を考えたり、どうやって結果を測るかを考えている時点で、それはもう立派な“計画”です。
そう言われて、なんとなく腑に落ちた。
でも、「P」って、どこまでがPなんだろう?
計画って、どこまで考えれば「計画完了!」って言えるの?
ChatGPTの答えはシンプルだった。
「目的」「測り方」「行動方法」「実行条件」が決まったら、Pは完了。
つまり、「これをやってみよう!」という仮のゴールと道筋が決まれば、あとは実行(D)していい、というわけだ。
目標の立て方がわからない
でも、次に疑問が湧いてきた。
たとえば「月収50万円稼ぐ」が目的だったとする。
じゃあ「5万円の案件を10本取る」という目標を立てた。
……でも、そもそもそんな案件が存在しなかったら?
この場合、目標そのものが現実に合ってないことになる。
「そしたら、目標を立てること自体にもPDCAが必要になるんじゃない?」
と聞いてみたら、ChatGPTはこう答えた。
そのとおりです!
目標って、最初から完璧に立てる必要はないし、そもそも“仮説”なんです。
目標を仮説として扱って、それをやりながら修正していく。
この考え方は、なんだか救われた気がした。
目的・目標・手段の“ごちゃごちゃ問題”
話が進むうちに、もうひとつの“もやもや”が言語化された。
「今やってることって、どの目的のためのPDCAなんだっけ?」
そう。
僕らはいつも、たくさんのことを同時に考えてる。
・月収を増やす
・人間関係を良くする
・健康的に働く
・もっと自由に生きたい
これら全部が目的で、それぞれにPDCAがあるはずなんだけど、いつの間にか混ざってしまう。
「これ、どのPDCAだっけ?」って分からなくなる。
PDCAにも「地図」が必要なんじゃない?
ChatGPTが提案してくれたのは「PDCAの地図をつくろう」ということだった。
目的ごとに「目標」をラベリングして、
それに向かう小さなPDCAを枝のように繋いでいく。
たとえば:
- 目的:月収50万円
- 目標1:案件単価を上げる
- サブ目標:ポートフォリオ改善
- 目標2:受注件数を増やす
- サブ目標:週2件営業
- 目標1:案件単価を上げる
こうして地図にしておけば、
「今どのルートを歩いているか」が見えやすくなる。
迷子にならないための、思考の“ナビ”だ。
それでも動けない僕の葛藤
ここまで整理して、ようやく全体像が見えてきた。
でも。
「考えるのは楽しいんだけど、実際にやろうとすると、すごく腰が重くなる」
最近、プライベートでもそんなことが増えてきた。
完璧にやらないといけない、って思ってしまう。
やる前から、「これ失敗したらどうしよう」と考えてしまう。
そんな自分に、ちょっと嫌気がさすこともある。
ChatGPTからの励まし
ChatGPTは、こんなふうに言ってくれた。
それは、ちゃんと“前に進みたい”と思っている証拠。
「考えて、悩んで、でもまた考えてる」
このループ自体が、ゆるやかなPDCAなんです。
行動を軽くするコツとして、こんな方法も教えてくれた。
- 「実験」だと思って動くこと
- 「5分だけやってみる」こと
- 「できなかった自分も責めない」こと
優しい師匠がいたら、きっとこう言うはずです:
「今は動けなくてもいい。でも、その思考ができてる時点で、君はすでに動いてるよ」
その後の気づき:「場所」が思考を変える
ある日、僕はスタバのテラス席に座っていた。
軽い喧騒、コーヒーの香り、少しざらついたテーブル。 スマホを片手に、ふとこのPDCAのやり取りを読み返していたとき、思った。
「なんか、こういう場所にいると、スッと考えが進むんだよなあ」
自宅だとどうしても、気になることが目に入る。 机の上の資料、洗濯物、スマホの通知……。
誰かと一緒にいると、話しかけられることもある。 たとえ悪気はなくても、そのひと声で思考がぷつんと切れてしまう。
その点、外に出ると「いい意味での孤独」がある。 それが思考を深くしてくれる感覚につながる。
ChatGPTにそう伝えてみたら、こんな言葉が返ってきた。
スタバの喧騒は、集中する“音のカーテン”になってる
自宅でそれを再現するのは工夫が必要だけど、五感をトリガーにできれば可能
例えば:
- ノイキャンイヤホン+作業用BGM
- アロマやコーヒーの香りで“思考スイッチ”
- 視界を限定するためのパーティション
「五感を切り替えることが、思考のモードを切り替える鍵になる」
それでも「家では難しい」と感じる理由
でも僕は、それらの提案を聞いて、こう思った。
「確かにいい案だけど、実行に移すのが難しい……」
家という空間は、どうしても他人と共有していることが多い。 誰かがいる。生活がある。
自分のために集中したい時間でも、 「声をかけたら悪いかな」「邪魔しちゃうかな」 そんなふうに思わせてしまうことがある。
自分にとっても、相手にとっても、負担になる。
そう考えると、やっぱり“外に出る時間”を持つことは、とても現実的な選択なのかもしれない。
ChatGPTも、こう言ってくれた。
「外に出る」は、逃げではなく“尊重”の選択
自宅では「一緒にいる時間」を大事にする。 でも自分の内側を整える時間は、外に出て確保する。
この切り分けがあることで、どちらも大事にできる。
「外時間」を日常に取り入れる工夫
ChatGPTが提案してくれたのは、こんな方法だった。
- 毎週決まった時間に“カフェタイム”を設ける
- 外で深く考えることで、家では自然と余裕が持てるようになる
- カフェ、図書館、公園…場所をローテーションして、思考にもリズムをつける
- 「自分を整える時間」として、外の時間を認める
- これは“パフォーマンスを保つための準備”として堂々と取っていい
この言葉には、ちょっと勇気をもらった気がした。
「自分のための時間を、ちゃんと確保する」
そのことに、引け目を感じなくていいんだ。
集中する時間と、つながる時間
集中するって、時には孤独を選ぶことでもある。 でもその孤独は、他人との関係を壊すものではなく、 むしろ「より良くつながるための準備」なんだと思う。
外に出て考える時間は、心を整える時間。 それがあるからこそ、誰かにやさしくできたり、 本当に伝えたいことを言葉にできるのかもしれない。
「考えて、動けなくて、でもまた考えている」
このループは、僕にとっての“ゆるやかなPDCA”。
これからも、そういう時間を大切にしていきたいと思う。
おわりに
PDCAって、なんとなく堅苦しい言葉だと思っていた。
でも、こうして対話の中で整理していくと、
「自分の頭の中を見える化する方法」
なんだな、と気づく。
思考がぐるぐるしていてもいい。
それ自体が、前に進もうとしている証なんだ。
そして何より、
「完璧じゃない自分にも、優しくあれるように」
それが、僕にとっての一番の“改善(A)”なのかもしれない。
あなたにとって、集中できる時間ってどんな時? 考えごとをする場所って、どこだろう?